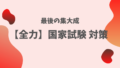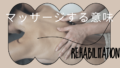各疾患には日本理学療法士協会が提唱する「理学療法ガイドライン」というものがあります。
過去の様々な研究や文献、論文から効果の有無や信頼性の高さを分類し、ガイドラインとして多くの理学療法士が作成しているもので、我々も臨床介入の参考にしています。
学生も、エビデンスのある介入をしていく必要があるので、ここでは分かりやすくエビデンスのあるもの(信頼性が高いとされているもの)をピックアップし、記載していきます。
教科書に載っていることも重要ですが、このガイドラインも重要ですのでぜひ臨床参加研修(臨床実習)の参考にしてください。
今回は脳卒中についてです。
▽こちらのページに移動しました▽
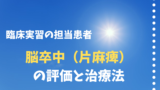
担当患者が脳卒中片麻痺になった臨床実習で役立つ「評価」「治療」のリハビリ
臨床実習で脳卒中患者の担当を受け持った時に役立てる記事です。効果的な評価・治療の流れを解説しています。