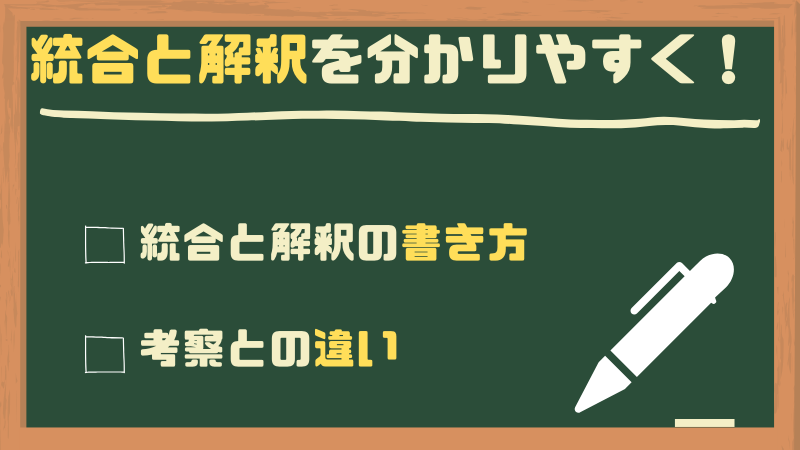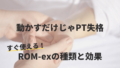この記事は『統合と解釈』の書き方についてお伝えしています。
レポートやレジュメで「統合と解釈」を書く機会があると思いますが、その書き方って学校では詳しく教わらないんですよね。
習ってないのに書けるわけないので、「統合と解釈の書き方」をなるべくわかりやすく解説します。
統合と解釈は「全ての情報から現状の答えを導き出す」ことです。
つまり、キミが実施した評価結果から、患者の問題点を導き出すこと。
言葉にすると難しいのですが、なるべく分かりやすく、例題を用いて解説します。
▽参考文献▽
「統合と解釈」の方法を解説
統合と解釈は、患者の「できない事」がなぜなのかを理学療法評価から結び付けて問題点を明らかにする作業です。
例えば「歩行困難な患者」がいるとします。
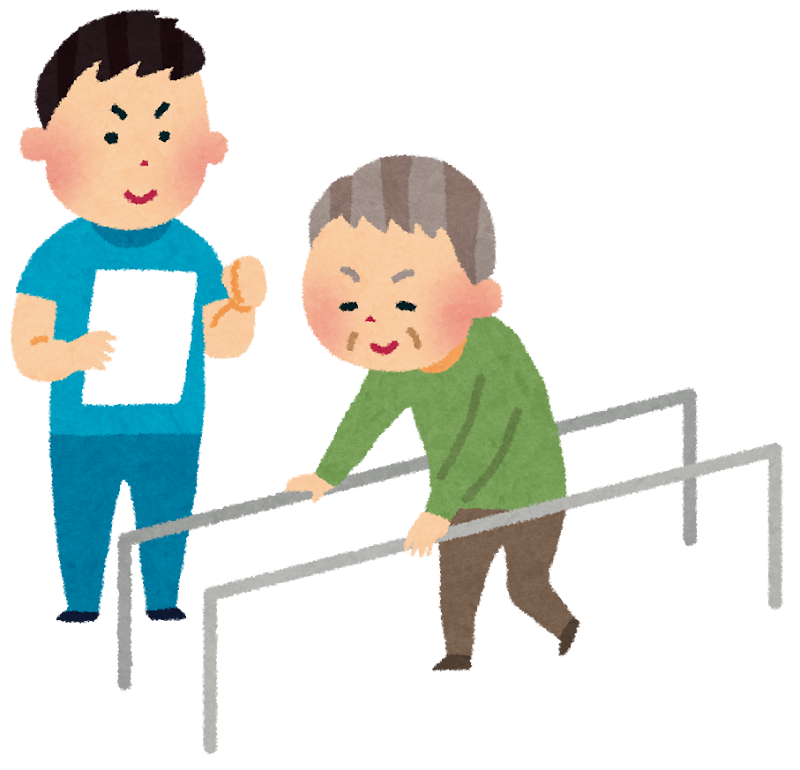
歩けない患者がいる
この歩けない患者の原因は何か?を評価から結び付ける作業が統合と解釈です。
【評価結果】
- 大腿四頭筋の筋力は段階3
- 大殿筋の筋力は段階5
- 可動域は全て問題なし
- 立脚中期に膝折れが発生する
- 脚長差なし
▽これらを『統合(まとめ)』する▽
【まとめた結果】
- 歩行困難は大腿直筋の筋力低下が問題である
- 歩行困難は立脚中期の膝折れが問題である
▽これらから『解釈(理解)』する▽
【解釈した結果】
- 歩行困難の理由は「大腿直筋の筋力低下」により「膝折れが発生する」ことである
以上の事から、歩けない理由=大腿直筋の筋力低下という事になります。
という事は
- 問題点抽出:大腿直筋の筋力低下による膝折れ
- 治療プログラム:大腿直筋の筋力強化
が導き出されます。
つまり統合と解釈をすることでより理論的に問題点の抽出が可能になるという事です。
このように、評価結果を照らし合わせて、患者像を捉える行為を統合と解釈と言います。
統合と解釈の書き方を解説
統合と解釈を書くには、書く順番が重要です。
順番がメチャクチャになると、とても読みにくい文章になってしまいます。
統合と解釈を書く順番
- 症例の説明
- 着目したポイント
- 着目ポイントの問題点
- 評価との照らし合わせ
- 改善に必要な要点
上記の流れで書いていきます。
レポートやレジュメの作成に使えますので、ぜひ参考にしてください。
①症例の説明
まずは症例の大まかな全体像を説明していきます。
本症例は〇月〇日に自宅で転倒し、大腿骨頸部骨折を呈した70歳代の女性である。
既往歴はなく、病前は自立した生活を送っていた。
②着目したポイント
次にこの症例にたいして、あなたが着目したポイントを記載します。
痛みや動作、本人の主訴やhope、家族のhopeなどと組み合わせて話を展開させていきます。
HOPEは自宅復帰で、同居の夫もそれを強く望んでいる。
現在のADLは杖歩行見守りで身の回り動作も自立しているが、本人の役割である家事と共に、趣味の婦人会への参加も強く希望されている。
現在の歩行能力では家事全般を行ったり、徒歩10分の集会場で行う婦人会に参加するのも困難であるため、歩行能力について述べていく。
③着目ポイントの問題点
次に、着目ポイントの問題点を述べていきます。
本症例の歩行能力は杖歩行見守りで50mの連続歩行可能。
歩行後は疲労感を訴え、心拍数も上昇傾向にある。
また、時折ふらつくことがあるため見守りは外せない。自宅復帰するには、歩行距離の延長とふらつきの軽減が必要になる。
④評価との照らし合わせ
仮説を裏付けるために評価と照らし合わせをします。
下肢筋力検査の結果、大腿四頭筋、ハムストリングスは段階4~5で問題とならなかったが、中殿筋と大殿筋は段階3程度であった。
また、リハビリ開始前と終了後のバイタルチェックで、収縮期血圧が20mmHgの上昇、心拍数は30回/min上昇していたことから体力低下も疑われる。
⑤改善に必要な要点
問題点が上がったら、リハビリに必要な項目を羅列していきます。
以上の事から、中殿筋、大殿筋の筋力強化は必須であり、体力強化の為にエルゴメーターの実施を提案した。積極的なリハビリ介入により、動作は改善していくものと考えられる。
このような流れで書いていくと分かりやすいです。
文字数は10行以下に収まると良いかもしれませんね。
まとめると次のようになります。
統合と解釈のテンプレート
大腿骨頸部骨折を呈した70歳代の女性に対する統合と解釈
既往歴はなく、病前は自立した生活を送っていた。【目的とすべき動作】HOPEは自宅復帰で、同居の夫もそれを強く望んでいる。
現在のADLは杖歩行見守りで身の回り動作も自立しているが、本人の役割である家事と共に、趣味の婦人会への参加も強く希望されている。
現在の歩行能力では家事全般を行ったり、徒歩10分の集会場で行う婦人会に参加するのも困難であるため、歩行能力について述べていく。【動作の問題】
本症例の歩行能力は杖歩行見守りで50mの連続歩行可能。
歩行後は疲労感を訴え、心拍数も上昇傾向にある。
また、時折ふらつくことがあるため見守りは外せない。自宅復帰するには、歩行距離の延長とふらつきの軽減が必要になる。
【評価との照らし合わせ】
下肢筋力検査の結果、大腿四頭筋、ハムストリングスは段階4~5で問題とならなかったが、中殿筋と大殿筋は段階3程度であった。
また、リハビリ開始前と終了後のバイタルチェックで、収縮期血圧が20mmHgの上昇、心拍数は30回/min上昇していたことから体力低下も疑われる。
【改善に必要な要点】
以上の事から、中殿筋、大殿筋の筋力強化は必須であり、体力強化の為にエルゴメーターの実施を提案した。積極的なリハビリ介入により、動作は改善していくものと考えられる。
このように、統合と解釈は「患者の希望やリハ目的に対して、現在の評価から問題となるポイントを洗い出す」作業になります。
統合と解釈を書くタイミング
統合と解釈を書くタイミングは評価の後です。
「評価」→「統合と解釈」→「治療プログラム」→「考察」の流れになります。
統合と解釈と考察は全く別の物なので、分けて書くべき。
統合と解釈は「問題を洗い出し、治療プログラムを立案する」までのプロセスを差すので、考察とはちょっと違うんですよね。
考察に関してはこちらの記事をご参照ください。
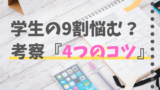
実習レポートは「統合と解釈」と「考察」どっちを書けばいいの?
実習レポートやレジュメは文字数が限られていますので、考察でまとめて書いてしまうほうが良いです。
考察の出だし10行以内で統合と解釈を記載し、その後考察に移っていけば比較的読みやすいレポートやレジュメが完成するはず。
あとは臨床実習指導者に相談し、適宜修正していく事をおすすめします。
わからなかったらまず相談ですよ!