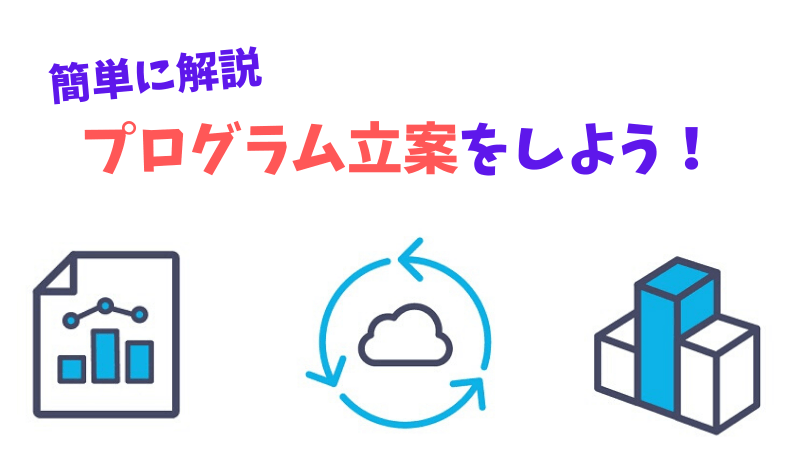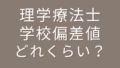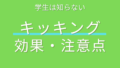「評価は終わったけど治療プログラムの立て方が分からない…。」
そんな悩みを解決します。
治療プログラム立案は臨床実習においてかなり重要な位置づけであり、かなりの確立で学生が悩む項目の1つとなっています。
でも治療プログラム立案ってそんなに難しく考える必要はありません。
まずは大まかにプログラムを立案していき、実行していくべきです。
ここでは、簡単に理学療法プログラムを立てていく方法をお伝えします。
理学療法プログラム立案の準備(評価)
プログラム立案をするには、まず評価が必要です。
患者の疾患に沿った評価を実施し、結果から問題点を探し出していきます。
【主な評価項目】
- 対象者情報
- 痛みの質
- 視診・触診
- 肢長周径
- 認知機能検査
- 関節可動域測定
- 筋力測定
- 感覚検査
- 整形外科テスト
- 片麻痺機能検査
- 筋緊張
- 姿勢観察、動作観察
- ADL評価
評価が終わったら、その結果から統合と解釈を行い、問題点を抽出します。
評価結果から読み取るには以下のポイントを押さえると理解しやすいです。
- 参考可動域やカットオフ値より低い項目がある
- 左右差がある
- 一般的な年代の数値より劣る
カットオフについてはこちらの記事をご参照ください。
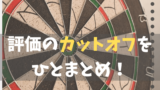
実際に評価して「一般的数値より劣る部分」や「左右差がある部分」が、この患者の問題点となります。
※ゴール設定やhopeによって問題点は変わります。
治療プログラムを立案するためには「評価して問題点を洗い出しておく」必要があるんです。
問題点を洗い出せないと理学療法プログラムは立案できません。
患者がどうなってほしいか考えよう(hope)
評価から「劣る部分」を見つけたら次に「この患者にどうなってほしいか」を考えてみてください。
患者のhopeから考えても良いですし、家族のhopeを参考にしても構いません。
ここでは患者の最終的な理想像をイメージしてください。
- 杖を使わず歩けるようになってほしい
- トイレに1人で行けるようになってほしい
- 自宅で1人で生活できるようになってほしい
いろいろあると思いますが、基本的に目標は「1つ」に絞ったほうが考えやすいです。
問題点を1つに絞ることで学生は治療プログラムが立てやすくなりますから。
実際に理学療法プログラムを書いてみよう
目標が決まったら、その目標が達成できていない原因を評価結果から抜き出します。
- 杖を使わずに歩けない→中殿筋と大殿筋のMMT3
- トイレに1人で行けない→BBSがカットオフ以下
- 自宅で1人で生活できない→Brsステージ3
もちろん、目標が達成できていない原因は1つではありませんから、自分が「問題だ」と思う項目を全て洗い出すんです。
そうすると、それを改善させるためのプログラムが立案できるというわけです。
理学療法プログラムの注意点
例えば「関節可動域の低下」があるから「関節可動域エクササイズをする」というのは間違いです。
それは治療プログラムとは言えません。
膝の屈曲制限ってなんで起こるんでしょうか?
- スクリューホームムーブメントの消失
- 膝蓋骨の動きの悪さ
- 筋肉の過緊張
- 痛み
- 腫脹
- 浮腫
- 皮膚・筋の短縮
これらが原因となります。
僕たちは膝の屈曲制限の原因を考え、それに適した治療プログラムを立てなければなりません。
膝の屈曲制限=可動域制限ではありません。
膝の屈曲制限の原因によって治療プログラムは変化するハズ。
- スクリューホームムーブメントの消失→正しい関節運動の学習
- 膝蓋骨の動きの悪さ→パテラの可動性を出す
- 筋肉の過緊張→ホットパックなど
- 痛み→除痛
- 腫脹→圧迫・挙上・冷却などによる緩和
- 浮腫→圧迫・挙上・温熱などによる浮腫除去
- 皮膚・筋の短縮→ストレッチ
膝の関節可動域低下に対する治療プログラムを考えると、原因によって実施するプログラムが変わります。
学生にはここを目指してほしいんです。
膝の屈曲が制限されている、という事実から、もう一歩踏み込んでください。
「なんで屈曲が行かないんだろう?」と、踏み込んで考えると、さらに良い治療プログラムが立案できます。
認知症患者への理学療法プログラム立案
認知症患者への理学療法プログラムは難しいです。
とくに学生にとってはハードルが高いのですが、「自分がなんとかしなきゃ!」と考えないほうがいいですよ。
リハビリで何とかするんじゃなくて、環境でなんとかしてしまえばいいんです。
認知症は良くなりませんから。
たとえば「車いすのブレーキを必ず忘れてしまう」という認知症患者に対してどうアプローチするか。
方法はいくつかあると思います。
- 毎回声掛けして認識してもらう
- ブレーキを掛ける練習をする
- ブレーキレバーを延長する
- 張り紙をする
その患者にとって、どれが適切か?を考えてみて、実行していきます。
ここで注目してほしいのが1,2はリハビリ中に練習できますが、3,4に関しては特にリハビリの訓練とは言えませんよね。
環境を変化させることで、対処しようとする例です。
このように、リハビリの手技でどうにかするのでなく、環境設定を変えることでなんとかするのも治療プログラムとしては重要です。
「治療」という言葉に惑わされないように。
もしも、どれも不可能だったらどうしましょう。
そしたらもうこうするしかありません。
- ブレーキを掛けなくても立ち上がれるような練習をする
- 車いすを外す
つまり立ち上がり練習や歩行練習をたくさんして、ブレーキのかかってない車いすから立てる能力を身に付けたり、車いすを利用しない生活を目指すというもの。
こんなアプローチだって良いと思いますよ。
認知機能や高次脳機能はなかなかすぐに改善しません。
でも、キミが1か月という短い期間で患者に改善を求めるなら、なるべく早く効果の出る方法を考えていきたいですよね。
その他にも…
- 日付を忘れる→カレンダーを一緒に作る
- 左半側空間失認→環境整備
- 恐怖心→痛みのない動作、安心できる動作を理解させる
- ストレス→外気浴、散歩、レクリエーション活動の参加など
正解はありませんので、いろいろな事を試したり、CEに相談してみてください。
学生はどんな運動があるのかを勉強しよう
学生が治療プログラムを立てられない理由は「プログラム」を知らないからです。
例えば筋力強化をしたいと思っても、多くの学生は、筋トレの方法を知りません。
「大殿筋鍛えて」と言っても、何をしていいか分からない人が多いのでは?
解剖学や運動学を知っていても、実際に運動の方法をしっていなければ治療プログラムは立てられません。
まずは、運動を知るべきです。
今は良い時代なので、インターネットやyoutubeにいくらでも運動方法は出ていますので、どんな運動があるのか勉強しておく必要があります。
特にアスレティックトレーナーやビルダー系のなどの参考書を読むと、たくさんの筋トレ方法が載ってるのでおすすめ。
教科書や参考書が無くても、小・中・高校でやった運動を参考に出来ます。
柔軟体操や、筋トレ、運動などはいろいろと習っているはず。
それを応用しましょう。
腕立て伏せや腹筋、スクワットなどは誰でも知っている運動ですよね。
ラジオ体操なんかも、誰でも知っています。
その動作をリハビリに応用しましょう。
ラジオ体操はダイナミックストレッチの部類に入るので、一度通して体操してみてどこが伸びるかを確認してみるといいかもしれませんね。
さらに理学療法学生は、MMTの教科書を参考にすることもできます。
MMTは教科書を開くと、どこの筋を評価するのか?が書かれています。
つまり、MMTと同じ動きをすれば、対象となる筋が鍛えられるんです。
それを思い浮かべれば簡単ですね。
大殿筋を鍛えてと言われたら、MMTの大殿筋のページと同じ運動をさせればいいだけ。
腹臥位をとれない人用に、別法まで載ってるんだから活用しない手はありませんよね。
当然、ROMなら評価学のROM-テストのページを開いて、そこに載っている代償動作に気を付けながら動かしていくだけです。
参考可動域まで改善すれば全く問題ないでしょう。
理学療法プログラム立案の流れ
- 評価し、「劣る部分」を見つける
- 患者のhopeなどから目標を決める
- 目標を達成できない原因を評価結果から抜き出す
- 抜き出した「劣る部分」を改善させるためのプログラムを立てる
【例題】ある患者の理学療法プログラム立案例
左大腿骨頸部骨折患者に対する理学療法プログラム立案
【評価】
- Pain:左大腿外側、膝関節(動作時)
- ROM(Ltのみ):股関節屈曲90 伸展-10 外転20 内転10 SLR45 膝関節屈曲100 伸展-10
- MMT(Ltのみ):腸腰筋3+ 大腿四頭筋4 ハムストリングス3 内転筋2 中殿筋3+ 大殿筋3+ 腹直筋3
- M-tone:左大腿直筋 左大腿筋膜張筋 左中殿筋↑
- 整形外科テスト:左Ober-test(+) 左トレンデレンブルグ(+)
- 荷重量:体重43kg 制止立位時左下肢荷重量15kg 随意荷重量35kg
- アライメント:左骨盤挙上・後方回旋位 両膝外反膝
- 基本動作:起居:自立 起立動作:膝上に手置くと困難 移乗:見守り 歩行:歩行器見守り
【目標設定】
自宅での生活をほぼ自立しなければならない
【問題点】
- 機能障害:#1左大腿転子部骨折 #2術後 #3大腿筋膜張筋の短縮
- 能力低下:#4患側下肢痛 #5歩行能力の低下 #6下肢筋力低下 #7バランス能力低下
- 社会的不利:#8自宅での独立生活 #9 3階までの階段昇降 #10歩行補助具の使用
【治療プログラム】
- #左下肢ストレッチ(#1.2.4)
- #ステップ練習(#1.5.6.7)
- #Active-ROM(#1.2.4.)
- #跨ぎ動作練習(#5.7.8.9)
- #歩行練習(#5.6.7.8.9.10)
- #階段練習(#5.6.7.8.9.10)
()内は問題点に対するもの
さいごに治療プログラムの書き方アドバイス
治療プログラム立案は、最初はそこまで細かく設定しなくてもいいです。
- ブリッジエクササイズを30回
- 階段昇降を30回
- 股関節のROMを20回
などと立ててくる人がいますが、最初は
- 大殿筋の筋トレ
- 階段練習
- 股関節ROM
というように大まかに設定してください。
治療を続けていくうちに「この患者のブリッジは20回くらいが適正だな?」と分かってきますから。
まず大事なのは、評価から違和感を感じ、患者の目標に向かって改善すべきプログラムを立てることです。
治療プログラム立案に正解はありません。
問題点が改善すれば、どんな方法でもOKだと思います。
ただ、問題点が「なぜ」起きているかを考えなければ、治療プログラムを立ててもバイザーからは不満に思われるでしょう。
可動域が上がらないのはなぜか?
それを考えた結果、治療プログラムは立案できるんです。
指導者から「もっと深く考えろ」と言われるのはそういう事だと思います。
そして、治療の方法も沢山学んでください。いまでは教科書以外にもyoutubeでも色々な運動方法が出ています。
その方法が本当に効果があるかはわかりませんが、参考にする価値はあると思いますよ。
困ったらネットで調べてみてくださいね。
たとえば「大殿筋 鍛え方」「大殿筋 腰痛あり 鍛えたい」とかね。