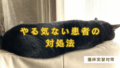ADL(Activities of Daily Living=日常生活動作)は、PTが実習や臨床で必ず向き合うキーワードです。
単に「食事ができる/できない」だけを見ていても不十分。
患者さんが家で自立して暮らすには、動作に至るまでの「プロセス」を細かく評価して、足りない機能や環境の工夫を見つけることが大切です。
この記事では、リハビリ学生が実習で使えるように、ADLを“困るポイントから考える方法”と具体的な細分化・評価法を分かりやすく解説します。
ADLを「できる/できない」で終わらせない — 困るポイントから考える
ADLの代表5項目(食事、整容、更衣、排泄、入浴)が全部できればOK、ではありません。
日常生活で重要なのは「その作業に至るまでの過程(準備・移動・後片付け)」です。
- 食材の準備ができない
- 食器をテーブルまで運べない
- 食後に片付けられない
といった問題があると、実際の自立は難しい。
まずは「どこで困るか」を洗い出すのが評価の起点です。
動作分析の基本:自分ごとで考える(朝起きたら何をする?)
理学療法士は“動作のプロ”。
まず自分の朝の動作を具体的に書き出してみましょう。
まず私は『時計を見ます』時計は携帯電話で確認するので、朝起きてまずする事は『携帯電話を探す』です。
その後、時間を確認したら起き上がります。
床に布団を敷いて寝ているので、まず『側臥位』⇒『四つ這いになって』⇒『立ち上がります』。
その後、『布団を真っ直ぐになおし』⇒『洗面所に2m程歩いて向かいます。』
- 眼を覚ます
- 手を伸ばして携帯を探す
- 携帯を掴んで顔の前に持ってくる
- ホームボタンで時間を見る
- ベッドから起き上がる(側臥位→四つ這い→立ち上がり)
- 布団を整える→洗面所へ歩く(約2m)
この「順序」と「各動作に必要な能力」を明確にすることで、どこが障害なのか、どこを評価すればいいかが見えてきます。
「時計を見る」までに必要な能力と評価項目(具体例)
上の例をもっと細かく分解すると、評価すべき能力が出てきます。
1:『手を伸ばして手さぐりで携帯電話を探す』ことから始めます。
携帯電話の手ごたえがあれば
2:『携帯電話を把持し、顔の前に持ってくる』という動作をします。
携帯電話の操作は
3:『片手でホームボタンを押す』ことでホーム画面の時計を見る事ができます。
ここで考えられる必要な能力は
- 『手を伸ばして探る能力』
- 『把持能力』
- 『携帯電話を持ってきて顔の前で止める能力』
が必要となり、それを必要な身体機能に表すと
- 『肘の屈伸』
- 『肩の屈曲・内外転の自動運動、水平屈曲』
- 『手内筋の随意収縮』
- 『関節のコントロール(深部感覚)』
- 『表在感覚』
となります。
- 手を伸ばして手探りで携帯を探す
→ 必要能力:肩の屈曲・肘伸展、触覚(表在感覚)、空間認知 - 携帯を把持し顔の前へ持ってくる
→ 必要能力:把持力(手内筋)、肘・肩の協調、姿勢制御 - ホームボタンを押す(片手操作)
→ 必要能力:巧緻性、指の随意運動、視覚機能
身体機能レベル(ICF)に落とすと
#筋力(MMTで簡易評価)
#深部感覚(位置覚)・表在感覚
#手指の巧緻性(9ホールや簡易把持テスト)
#立位・移乗のバランス(TUG、立ち上がり観察)
となります。
このように徐々に細分化させることで『何が必要か』が分かり、評価から『何が足りないか』と求め、『治療プログラム』を立てることになります。
これらを評価して「何が足りないか」を明確にし、それに基づいて治療プログラムを組みます。
環境的工夫とOTとの連携
能力的に難しい場合、環境を変えることで自立が可能になることが多いです(例:ベッドの高さ調整、手すり設置)。
作業療法士(OT)は日常生活の環境調整や道具選定が得意。
連携してゴール(例:安全にトイレに行ける状態)を共有しましょう。
実習で使えるADLチェックリスト
- 起居:寝返り、起き上がり、座位の流れを確認
- 移動:歩行距離・補助具・扉操作の可否を確認
- 手指機能:把持力・巧緻性を簡易でチェック
- 感覚:表在感覚・位置覚の有無チェック
- 環境:家具配置・段差・ドア種類(引き戸/開き戸)を記録
- 家族支援:家族がどこまで手伝えるか確認
実習で記録シートとして使えるように短くまとめておくと便利です
まとめ:細分化して評価→環境+訓練で自立へ
ADLは単なる「できる/できない」判定ではなく、動作を細分化して何が不足しているかを見つけることが鍵です。
そこから「訓練」「環境調整」「他職種連携」へとつなげるのがPTの腕の見せどころ。
実習ではまず自分の生活動作を分解してみるところから始めましょう。
学生のうちにこのクセをつけると臨床で絶対に役立ちます。