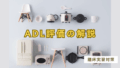リハビリって、PT(理学療法士)が治療したからといって自動的に良くなるわけじゃありません。
実は、一番大事なのは 「患者さん自身のやる気」。
やる気のない人にいくらリハビリをしても良くなりません。
でも正直なところ、患者さんにやる気を出してもらうのって簡単じゃないんですよね。
だって、入院や通院を「好きでやってる!」なんて人はほぼいませんし、「リハビリ楽しみ!」っていう人も少数派です。
そこで大事なのが、段階的なアプローチ。
いきなり「頑張りましょう!」ではなく、ステップを踏んでやる気を育てていくことが必要なんです。
この記事では、「やる気ゼロの状態から少しずつモチベーションを引き出す方法」 を、PT目線でわかりやすく解説していきます。
学生さんや新人PTにも役立つ内容なので、実習や臨床現場でそのまま使えますよ。
最低限のやる気:生きる強さはありますか?
患者さんも、一人の人間として「生きる力」を持っています。
でも、その力を 自分の意思で発揮できているか? がポイント。
ここでいう「生きる」とは、心臓が動いているとか呼吸してるといった生理的なことではありません。
たとえば…
- お腹がすいたら「食べたい」と思って自分で食べる
- トイレに行きたいから行く
- 眠いときに自分で寝る
こういう 日常の基本的な行動を、自分の意思で選んでできるかどうか です。
経管栄養や尿器を使っていても大丈夫。
大切なのは「選んで行う姿勢」があるかどうか。
もし全てが受け身で「生かされているだけ」の状態だと、やる気を引き出すのは難しいです。
報酬を使ってやる気を引き出す方法
やる気を出す1つめの方法として、「報酬」をうまく使うこと。
報酬といっても、お金だけじゃなくていろんな形があります。
- 物:ちょっとした贈り物
- 余暇:好きなことをする時間
- 食事:ご褒美の食べ物
- 承認:褒められること
子どもに「勉強が終わったら遊んでいいよ」と言うのと同じで、何かメリットを提示すると人は動きやすくなるんです。
しかし注意して欲しいのは、このやる気は、なんらかのメリットがあるからやる気を出すので、その報酬(メリット)がなければやる気は出ない、という事になります。
有名な実験があります。
パズル好きの子どもをAグループとBグループに分けました。
- A:そのままパズルを解く
- B:パズルを解いたら報酬(お金)を与える
結果、Bグループの方がよくパズルを解きました。
つまり、報酬によって一時的にやる気が上がったんです。
ところが報酬をなくしたらどうなったか?
- Aはそのまま楽しんでパズルを続けた
- Bはパズルをまったくやらなくなった
報酬を無くすとやる気が無くなり、いままで好きだったものもやらなくなったしまった、という実験でした。
つまり「報酬によるやる気」は爆発力はあるけど、持続力はないんです。
だからあまり頻繁には使えないんですよね。
内的な報酬を活用してやる気を育てる方法
やる気を出す2つ目の方法が、「内的動機付け」 です。
これは「自分の意思で行動することで得られる喜びや意味」で、外から与えられるものではありません。
内的報酬の例
- これをやれば上手くなる
- これをやれば誰かの役に立てる
- これをやれば誰かが喜んでくれる
- これをやれば自分の生活が楽になる
スポーツ選手が毎日練習を続けるのも、母親が赤ちゃんの世話を頑張るのも、この「内的動機付け」があるからなんです。
リハビリでの内的報酬
リハビリの場合も同じ。
- リハビリをすれば痛みが軽くなる
- リハビリをすれば歩けるようになる
- リハビリをすれば家に帰れる
こういう「自分で見つけた意味」が患者さんの中に育つと、やる気は長く続きます。
報酬みたいに即効性はないけど、持続力は圧倒的に強いんです。
だからみんなは、こういった内的動機づけを活用して患者にやる気を出してもらう必要があります。
まとめ:PTにとって最初の仕事は「やる気を出させること」
PTは「患者さんを治す」ことはできません。
本当に治していくのは、あくまで患者さん自身の力です。
だからこそ、リハビリを拒否されてしまったら意味がありません。
PTの最初の仕事は「やる気を引き出すこと」。
そのために大切なのは…
- 最低限の生きる力を確認する
- 外的報酬をうまく使ってきっかけを作る
- 内的報酬を育てて長く続けられるモチベーションに変える
声かけ一つでも変わります。
たとえば…
- 「今日のリハビリでここまで歩けたら、明日はもっと楽になりますよ」
- 「リハビリを頑張れば、早く家に帰れますよ」
こういう言葉が患者さんの心に響けば、やる気は自然と湧いてきます。
つまり、PTの本当の仕事は「治す」ことじゃなくて、「やる気を出させて一緒に歩むこと」なんです。
実習や臨床の現場できっと役立ちますよ。