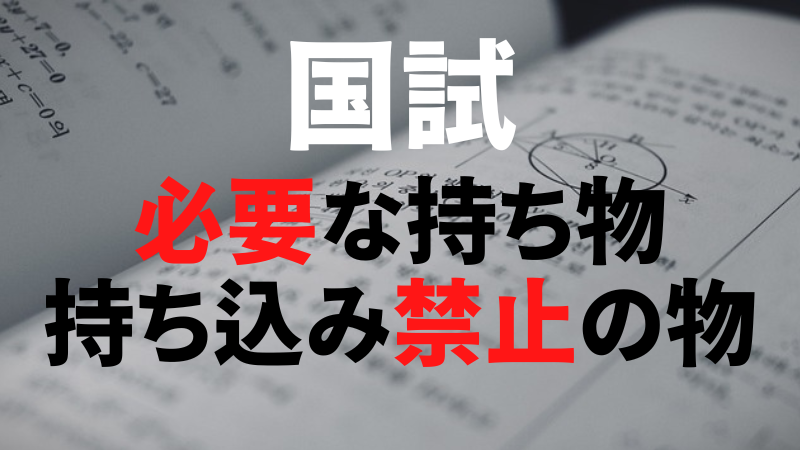理学療法士国家試験が近づいてきました。
国家試験の当日に必要な持ち物と持ち込みできない物を紹介します。
普段使っているものでも、試験会場には持ち込めないものもあります。
ぜひ受験の準備にこの記事をお役立てください。
国家試験の受験に絶対に必要な物
- 受験票
当日の朝にも確認必須!それ以降はカバンから出さない! - 会場までの地図
ネットで経路を確認すべき! - お金
万が一の為にタクシー代5,000くらい! - 筆記用具
鉛筆×5消しゴム×2くらいは予備として持っておく! - マスク
マスクをしていないと受験できません!
なくても国家試験は受けられるけどあると便利な物
- 腕時計
会場内に時計はありません、スマホ禁止 - 昼食
あまり食べすぎないように軽めに!眠くなるよ! - 参考書・ノート
直前の復習に!お守り代わりに! - スマホ・携帯電話
緊急連絡用、学校の番号と試験会場の番号も登録しておこう! - 上着
ひざ掛け推奨!会場は寒いぞ! - ハンカチ・ティッシュ
花粉が飛び回る季節、衛生対策にも! - メガネ
コンタクトの人もメガネは持っていこう! - おやつ
栄養補給に糖分が必須! - 常備薬
特に花粉症の人は必須 - ヘアピン・ヘアゴム
髪の毛が邪魔で集中できないこともある!
これがあればメチャクチャ国試に有利!
マスクは何でもOKではありません。
基本的には不織布マスクが推奨され、スポーツマスク等はダメな場合もあります。
また、呼吸しやすいマスクを選ぶことで試験にも集中できます。
立体型のモノを選ぶと良いと思います。
コンパクトに持ち運べるひざ掛けは必須です。
ただし、柄や英語がプリントされているものはカンニングが疑われるので、無地のモノを選びましょう。
カイロも持っておくと便利です。
今では充電式のカイロもあるので、こちらもおすすめ、なんとスマホの充電も出来ちゃいます。
薬やサプリメントの持ち運びに便利なピルケース。
国試後にも使えます。
特に咳止め・鼻炎薬はなくなると一大事なので、しっかりと管理しておきたいですよね。
カンニング防止の観点から、アップルウォッチを中心としたスマートウォッチの持ち込みは禁止です。
また、アラーム機能や1時間ごとに音の出るデジタル時計も禁止です。
音を消してあればデジタル時計でもいいですが、アナログ時計を持っていたほうが安心かもしれません。
アナログ時計を身に付けてるとカッコいいしオシャレに見えますし。
おやつにエネルギー補給するにはチョコレートが一番。
その中でも超おすすめなのがこちら、【ネスレ ミロ ナゲッツ 食べるミロ 】。
Twitterでも「疲れにくい」「寝つきが良くなる」「貧血がよくなる」など話題沸騰した栄養補給のお菓子です。
単にチョコレートを食べるより効率アップします。
試験だけじゃなく、日ごろからおやつ代わりに食べることを超おすすめします!
試験会場に持ち込めないもの
- 帽子
持ち込んでもいいけど着用は不可、顔が見えないので。ニット帽もダメ。 - 耳栓
試験官や緊急時の指示が聞こえないのでダメ。もちろんイヤホンとしてカンニングも疑われる。 - スマートウォッチ
カンニングが疑われるのでアップルウォッチ系は禁止 - ボックスティッシュ
机の上は筆記用具と受験票のみ出しておける。ポケットに入るなら可。 - パソコン・デジカメ・スマホ
これらは会場内でバッグから出すことができない
以上です。
国家試験当日、忘れ物の内容にしてくださいね!