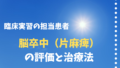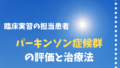各疾患には日本理学療法士協会が提唱する「理学療法ガイドライン」というものがあります。
過去の様々な研究や文献、論文から効果の有無や信頼性の高さを分類し、ガイドラインとして多くの理学療法士が作成しているもので、我々も臨床介入の参考にしています。
学生も、エビデンスのある介入をしていく必要があるので、ここでは分かりやすくエビデンスのあるもの(信頼性が高いとされているもの)をピックアップし、記載していきます。
教科書に載っていることも重要ですが、このガイドラインも重要ですのでぜひ臨床参加研修(臨床実習)の参考にしてください。
今回は変形性膝関節症についてです。
変形性膝関節症は加齢、肥満、遺伝的因子、力学的負荷など多くの原 因が関与して発症する多因子疾患である
【参考書】
変形性膝関節症(OA:Osteoarthritis)の臨床実習で必須の理学療法評価
変形性関節症に有用な理学療法評価をピックアップします。
変形性膝関節症の患者情報
- 問診
:①年齢②性別③疼痛部位④受傷機転⑤腫脹(水腫・血腫)⑥仕事⑦運動歴 - 既往歴
:①ACL 損傷、再建術の有無②半月板損傷、部分切除と全切除の有無 - 変形性膝関節症のリスク
:①肥満②膝の外傷③仕事④趣味 - 肥満
:①身長②体重③BMI
変形性膝関節症の画像検査
- 単純 X 線検査(Kellgren-Lawrence grading: K-L 分類)
- 磁気共鳴画像検査(magnetic resonance imaging: MRI)
一般的にX線画像と、必要に応じてMRIにて軟骨や靭帯・半月板の状態の評価を行います。
X線画像の撮影方法として、正面像・側面像・膝蓋骨軸射像(スカイライン像)を確認し、左右を比較すべきです。
必要であればトレーシングペーパーを使い、画像を模写します。
- FTA:大腿骨長軸と脛骨軸から生じる角度であり、正常なら約175°
- Mikulicz線:大腿骨頭中心と足関節中心を結ぶ線であり、正常なら膝関節の中心を通る
- 関節裂隙の狭小化:内側・外側の関節の広さ
- 骨棘:関節面の出っ張り
- 骨硬化:骨の白い硬化部分
- 膝蓋骨の変位:内側・外側の変位
- 大腿骨・脛骨の変位:内側・外側どちらに変位しているか
変形性膝関節症の理学所見(客観的評価)
- 下肢アライメント
- 疼痛
- 膝関節周囲筋の筋力評価
- 股関節,足関節・足部周囲筋の筋力評価
- 胸郭・脊椎・骨盤との関係に関する評価
- 歩行評価
:歩行速度,ストライド,ケイデンス
:下肢関節の運動学的変化
:下肢関節の運動力学的変化
:外側スラスト
:筋活動 - 生活機能の評価
:FIM
:Barthel index - 健康プロファイル型尺度の評価
:MOS short-form 36(SF-36)
:Japanese knee osteoarthritis measure(JKOM) - 課題遂行テスト(performance test)
:timed up and go test
:6分間歩行テスト
変形性膝関節症(OA:Osteoarthritis)に効果のある治療法、リハビリの流れ
変形性膝関節症のリハビリでエビデンスの高いものをピックアップしています。
もちろん、ここに載っていない治療法も効果がある場合が多いですので、参考までにどうぞ。
変形性膝関節症の保存的治療の理学療法介入
- 患者教育と生活指導
:運動を含む自己管理プログラム指導
:食事指導 - 減量療法
:BMI28以下を目標 - 運動療法
:筋力増強運動
:有酸素運動
:協調性運動 - 徒手療法
- 足底挿板療法
:変形の著しい症例に対して効果あり - 装具療法
:膝サポーターの使用 - テーピング
:疼痛に対するもの
:機能障害に対するもの - 物理療法
:超音波療法
:温泉療法
:TENS 療法(transcutaneous electrical nerve stimulation: TENS)
:水治療法(hydrotherapy)
:干渉波治療(interferential current therapy)
:レーザー治療
:物理療法の複合使用と運動療法との併用
運動療法
一番重要なのは大腿四頭筋の訓練などで筋力強化を行い、関節を安定させ、荷重が内側と外側に均等に掛かるようにすること。
有酸素運動も効果的であり、筋力強化と有酸素運動は米国整形外科学会(AAOS)と日本整形外科学会(JOA)でも高いエビデンスレベルを示しています。
有効性が認められた運動療法は
- 大体四頭筋訓練
- ハムストリング訓練
- 股関節周囲筋群訓練
- 足関節底背屈訓練
- 腹筋・背筋訓練
- 上腕二頭筋・大胸筋訓練
- スクワット
- CKC exercise
- 等速性運動
- セラバンド
- 歩行
- 自転車
- 水中運動
など。
装具療法
足底板
内側型OAに対して、外側を高くした楔状タイプの足底板を使用するもの。
その傾斜角により、内反モーメントを減少させることでOAの進行を軽減している。
しかし、日本整形外科学会(JOA)では推奨されているが、米国整形外科学会(AAOS)では推奨されていない。
人種の差だろうか?
膝装具
軟性と硬性がある。
軟性はアルミ支柱の入った物や、スパイラルステーの入った物、内反矯正を行う伸縮ベルトが装用されている物などがある。
硬性は高価だが、装着の不快感から継続して装着する人が少ないと報告されている。
硬性の膝装具は患者の受け入れも悪いため、軟性の膝装具が用いられることが多い。
また、膝サポーターのほうが受け入れは良い。
有酸素運動
効果的な有酸素運動は、心拍数120~140前後が理想とされている。
ひざ痛のある患者であれば、(220-年齢)×0.6程度の負荷量に抑えたい。
ウォーキングは膝関節OA患者に対し、グレードAという高いエビデンスがあるのでぜひ取り入れたい。
散歩よりやや速めに歩き、4メッツ程度を目指すと良い。
変形性膝関節症の観血的治療後の理学療法介入
- 人工膝関節置換術(total knee arthroplasty: TKA)
:continue passive movement(CPM)装置(早期のみ)
: 関節可動域運動、スライダーボード運動(自動運動)
:漸増的筋力増強運動
:機能的運動療法、バランス運動
:術前の理学療法と患者教育 - 高位脛骨骨切り術( high tibial osteotomy: HTO )
:文献は見つからず
パテラモビライゼーション
膝関節の屈伸には膝蓋骨の滑車昨日は非常に重要です。
膝蓋骨は上下・内側への滑らかな可動性が必要なので、それをサポートします。
膝蓋骨の活動性の低下により、可動域制限を生じ、大腿四頭筋の筋力低下を招きます。
それを防ぐためにパテラのモビライゼーションは必要なのです。
パテラセッティング
大腿四頭筋の強化と、膝蓋骨の安定性を確保するための運動です。
足趾把持訓練
足趾把持訓練により、大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋との運動連鎖が起こり、下肢筋がうまく動かせるようになります。
タオルギャザーは膝疾患にも有効です。
変形性性膝関節症(OA:Osteoarthritis)のリハビリまとめ
変形性膝関節症の患者はかなり多く、多くの人に発症していることを知ってください。
例えば、大腿骨頸部骨折患者でも変形性膝関節症を合併していることが多いので、膝の状態は必ず見るべきだと思います。
変形性膝関節症患者の90%が保存療法なので、発見が遅れると膝痛として表れます。
どんな時でも、変形性膝関節症の存在を頭に入れておいてくださいね。
文献的には、筋力強化や運動療法は効果あり!というものが多いですが、日本での研究はあまり多くないようです。
治療しつつ試行錯誤も必要な疾患であることは間違いないですね。
【参考】