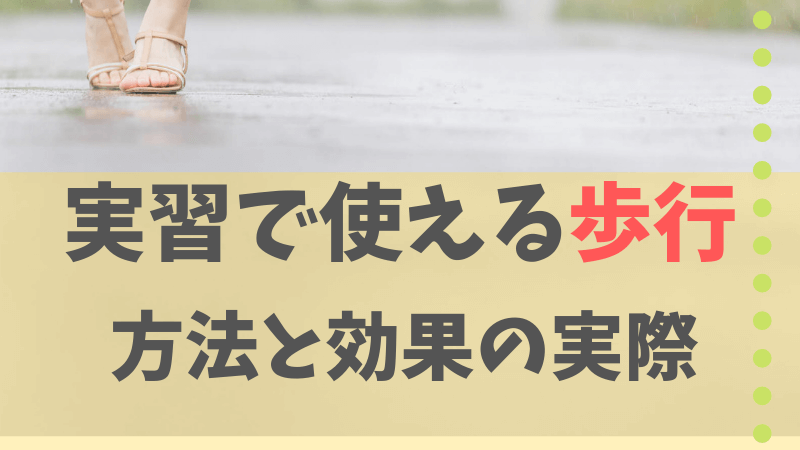実習でもよく歩行訓練を導入しています。
でもその目的や方法、注意点は理解していますか?
「歩行練習ってただ歩かせるだけじゃダメなの?」
「目的を持った歩行練習しろと言われても良くわからない」
歩行訓練はリハビリ初期から導入される重要な運動プログラムです。
たとえどんな疾患でどんな重症度であろうと、理学療法士はほとんのどの場合歩くことを目的にリハビリ介入をしていきます。
歩行は人間にとって重要な能力であり、歩行に必要な各能力(循環器・呼吸器・バランス・感覚など)は歩行以外の生活にも役立ちます。
ですので、理学療法士が歩行練習をするのは歩行獲得以外にも様々な目的を持って取り組んでいる場合が多いです。
しかし、学生はなかなかそこまで考えられないもの。
ここでは、実習で学生にやってほしい歩行訓練の方法や内容、その訓練の効果などを出来るだけ分かりやすくお伝えします。
ぜひ臨床実習でお役立てください。
歩行の評価の方法が難しくてできない!という方は、まずこちらの記事をどうぞ。

【参考書】
歩行訓練の注意点
歩行訓練の注意点は3つです。
- バイタル確認
- 介助する立ち位置
- 歩行距離の決定
この3つをまずは念頭に置いて訓練を実施しましょう。
①バイタル確認
まず歩行練習前にバイタル確認をします。
これを怠る学生がメチャクチャ多いので、マジで気を付けてください。
歩行は負荷量も多く、血圧変動や心拍数の変動が大きくなります。
歩行前にバイタルを確認し、歩行後にも確認します。
その差が大きければ、リハビリを中止したりする必要もあるので、本当に気を付けてください。
リハビリ中止基準は、こちらの記事でくわしくまとめているのでご参照ください。
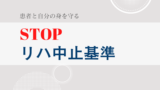
②介助する立ち位置
歩行訓練中は、どこに立てばいいかよく考えてください。
患者が転ぶとしたら、どの方向に倒れそうですかね?
何も考えず横に立っているだけではダメです。
当然、患側に立つ必要がありますが、転倒リスクのある方向が分かっていれば側方に立つのか、後方に立つのかが決まってきます。
また、介助量も腋窩介助なのか、手をつなぐのか、近位見守りなのか決まります。
患者にどのような介助・補助が必要なのか考えてください。
分からなければ、指導者と相談すると良いと思います。
③歩行距離の決定
患者がどれくらい歩けそうか、考えていますか?
なんとなく「あそこの椅子まで歩きましょう」と言っていませんか?
歩行訓練の目的の1つに、歩行距離の延長があります。
なぜその距離なのか、なぜその時間なのか考えて実施してください。
もちろん、バイタルを確認して、何メートルまでなら安全なのかを確認しておく必要があります。
最初は平行棒から始め、徐々に距離を延長していく必要があります。
とりあえず歩いてもらおう、という考えでは、かならず大きな事故に発展しますよ。
歩行訓練の方法
リハビリでの歩行訓練は、患者の身体機能に合わせて大きく4つの方法に分けられます。
- 手すりや平行棒を使用して歩く
- 装具や杖を使して歩く
- なにも使用しないで歩く
- 屋外や不整地を歩く
基本的にリハビリで歩行訓練をするときは「1→2→3→4」の流れで進めていきます。
これらの訓練内容を細かくお伝えしますので、対象患者に合った方法を試してください。
①手すりや平行棒を使用した歩行
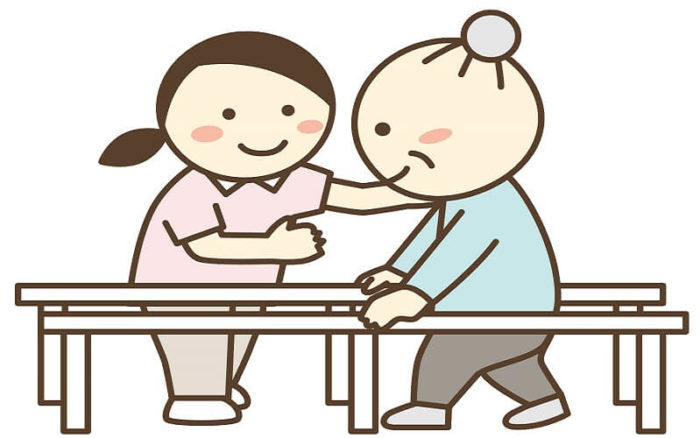
手すりや平行棒を使った歩行訓練は、患者の初期評価時や身体機能が改善しきっていない時に活用します。
まだ安全性が確立されていない場合は平行棒を使い、歩行の改善を目指します。
【適応】
- 免荷が必要な方の初期
- バランス能力低下患者
- 退院後は手すり歩行がメインとなる患者
- 入院初期の歩行練習
手すりや平行棒の大きな特徴は、免荷量が大きいことと、把持物(手すり)が固定されていることです。
平行棒の免荷量は0%~100%とコントロールできます。
免荷量は自分の上肢の荷重量で増減できる上に、支持基底面もかなり広く取れるので非常に安定した歩行練習が可能となります。
その為、バランスの悪い歩行訓練者でも安心して歩くことができます。
杖歩行の前の動作練習(杖→患側→健側)も平行棒内で1度練習するとスムーズに杖に移れる場合が多く、基本的には平行棒内から歩行訓練を開始します。
逆に、平行棒内歩行が適応しない患者は以下の通りです。
【平行棒内歩行困難な方】
- 把握反射が強い
- 過度のプッシャー傾向
- 重度の起立性低血圧
②装具や杖など自助具を使用した歩行
ある程度歩行の自立度が上がれば、装具や杖を使った歩行訓練を実施します。
入院患者は基本的にはこのレベルだと思って頂いてOKです。
ちなみに杖による免荷率は以下のようになります。
- 両松葉杖:100~25%免荷
- 片松葉杖:50~80%免荷
- ロフストランド杖:30%免荷
- T字杖:25~10%免荷
使用道具により免荷率は異なるので、患者の免荷率に合った道具を活用しましょう。
高齢者の中では松葉杖が使えない方も多いので、そういった方には歩行器を使うのもアリですね。
歩行器
このように、杖や歩行器を使用することで活動範囲が広がり、ADLも拡大します。
まずは杖歩行を目指すべきです。
【適応】
- バランス能力低下
- 機能不全(麻痺、変形など)
- 転倒歴がある
装具は機能不全がある方に利用します。
- 短下肢装具:下垂足、反張膝、軽度膝折れ、内反尖足など
- 長下肢装具:重度の膝伸展筋力低下、下肢支持性低下
- オルトップ:軽度下垂足、内反尖足など
【参考:下肢装具カタログ – 川村義肢株式会社】
いろいろありますので、疾患や変形、機能不全によって使い分けてください。
ただ学生には難しいと思うので、指導者と相談しながら使っていく事をお勧めします。
杖は歩行訓練をする際の基本となります。
特に転倒歴のある方は必ず修得させる必要があり、たとえ今後手ぶら歩行を目指していたとしても杖の使い方はレクチャーしておく必要があります。
平地歩行、段差またぎ、階段昇降の杖の使い方はぜひ練習してください。
【杖の特徴】
- T字杖:支持基底面を広げる。免荷量は体重の約20%
- 4点杖:支持基底面は広いが重く、4点をまっすぐつかなければいけないので少々使いにくい
屋外には向かないが、杖の基底部にベアリングがついていて不整地に対応したものもある - ロフストランド杖:握力の弱い方に適応。免荷量は体重の約30~40%と言われている
- 歩行器:持ち上げるタイプ(ピックアップ型)とタイヤがついているタイプ(車輪付き)がある
屋外用や、コンパクトな屋内用もある。免荷量は体重の約40~70%
③何も使用しない歩行(応用歩行)
杖などの歩行補助具を使用しない歩行(フリーハンド歩行)は、リハビリ初期~中期に導入します。
歩行評価やバランス評価で杖なしで歩けそうであれば積極的に導入しましょう。
フリーハンド歩行に移る目安
- 介助なしで45m以上歩ける(BIで歩行満点)
- バランス評価でカットオフ値を超える(BBS46点、FRT33cm、TUG13.5秒)
参考:調べるのが面倒なリハビリ評価のカットオフまとめ>>> - 痛み、膝崩れ、足底の引っ掛かりが無い
など
まずは平行棒内でフリーハンド歩行の練習をしてみることをおすすめします。
たとえ、退院後は杖歩行であっても、フリーハンド歩行の練習は実施すべきです。
リハビリでは日常生活より上のレベルを目指していかなければなりません。
退院後は杖歩行でも、フリーハンドで歩けるくらいの能力が無いと怖くありませんか?
そして、ある程度歩行能力が獲得できている場合は応用歩行も積極的に取り入れていきます。
【応用歩行の例】
- 大股、小股歩行
- 横歩き
- 後ろ歩き
- 継ぎ足し歩行
- ニーヴェントウォーク
いろいろな歩行にチャレンジしてください。
もちろん、安全面に配慮して行ってくださいね。
④リハビリにおける屋外歩行訓練の内容
屋外歩行は杖歩行を導入したあたりから積極的に行っていきましょう。
不整地歩行の練習にもなりますし、周囲環境への注意分配能力も必要になりますので、屋内歩行をするよりずっと疲れます。
屋外歩行の特徴を捉えることで、介助者の気持ちも分かりますし、家族指導の際も役立ちますよね。
屋外歩行で特に必要な項目は大きく分けて4つ。
- 不整地歩行練習(砂利道、点字ブロック、排水処理斜面)
- 坂道歩行練習(上り下り、左右の傾き)
- 舗装路環境練習(歩道の段差、グレーチング、マンホール)
- 社会的環境練習(対向者、横断歩道、信号、車など)
これらは自宅周囲の環境次第ではかなり重要となります。
しっかりと評価し、必要な訓練を導入してください。
また屋外の特徴として、道路は排水処理をするために道路中央が盛り上がり、歩道側に徐々に下がっていくという特徴があります。

排水の為に傾いている
目に見えない斜面で思わぬアンバランスが見受けられるかも?
また、グレーチングに杖を取られたり、マンホールで滑ったり、横断歩道が渡れなかったり、車の接近に気づかなかったり…(最近のクルマは静かなので特に注意!)
屋外には危険がたくさんあります。
だからこそ入院中に1度は実施しておかなければならない歩行訓練と言えます。
歩行訓練の効果
歩行訓練で得られる効果は
- 体性感覚の向上
- 心肺機能の向上
- バランス能力の向上
- 循環機能の改善
- 筋力の向上
- 体力の向上
とさまざまな効果があり、これを1次的な効果といいます。
これら1次的な効果が出て、身体機能が向上することで、2次的な効果が生まれます。
私たちが歩行訓練で目指す効果は、2次的な効果まで視野に入れ、を狙っていく必要があるということを覚えておいてください。
2次的な効果は、大きく4つに分類していきます。
- 歩行速度の向上による移動手段としての確立
- ADL上、必要な歩行能力の獲得
- IADL上必要な歩行距離の獲得
- 歩行の美しさ、スムーズさの獲得
もちろん、これ以外にも効果はあるのですが、学生が目指すべき効果は主にこの4つを覚えていてください。
①歩行速度の向上による移動手段としての確立
人間はなぜ歩くかわかりますか?
それは、移動したいから。
A地点からB地点に移動するために人間は歩きます。
移動する目的が無ければ歩く必要ありませんからね。
移動手段としては車いすもありますが、車いすでは行けないところも多いです。
自由に移動するためにはやっぱり歩行が重要なんです。
歩行訓練は、人間の最大の欲求である『移動したい!』にアプローチしています。
だから歩行できる(移動できる)とQOLがガツンと上がります。
ただし、ただ歩けるだけでは意味を成しません。
一般的な人間の歩行速度は80m/分です。
駅から5分と書いてあるお店は、駅から400m離れているという事になります。
対象者の歩行速度は、その速度に到達していますか?
最低でも、歩行速度は60m/分は欲しい所。
しっかりと評価しましょう。
ちなみに、10m歩行のカットオフは11秒6です。
これは1分間で51.7m進む速度なので、最低でもこれくらいは欲しい所ですよね、自宅に帰るなら!
歩行練習をすることで、移動手段として「歩行」が加わるので生活の幅がグッと広がりますよ!
移動したい!という欲求にこたえてあげてください!
②ADL上必要な歩行能力の獲得
移動の欲求の根底にあるのはADLです。
移動したい!という目的の場所の多くはトイレ、浴室、食堂など生活で必要な場所であることが多いです。
特にトイレ。
病院ならまだしも、自宅のトイレに車いすでラクラク入れる家がどれだけあるでしょうか。
家屋評価をしっかり行い、自室からトイレまでどれくらいの距離を歩ければいいのか、考える必要がありますよね。
歩いてトイレに行けるというのは人間の基本的な欲求を満たしたにすぎません。
ただし、患者家族が最も望むのが「トイレ自立」であることが多いです。
ADLを考えるのであれば、まずはトイレまでの移動を確保しなければなりませんよね。
③IADL上必要な歩行距離の獲得
IADLはADLよりさらに生活範囲を広げた状況を指します。
例えば、400m先のスーパーに行きたい!という欲求に対し、50mしか歩けなかったらリハビリは失敗です。
対象者のIADLを知ることで、歩行練習で歩行能力をどこまで向上させるべきかを考えていきます。
このあたりは、患者のHOPEからくみ取ってください。
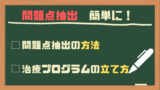
400m先のスーパーに行くなら、400m歩けてもダメですよ。
400mの往復と、スーパー内での移動が必要なので軽く1000mは歩けないとね。
もっと言うと、単に1000m歩けてもダメです。
周囲への気配り、車や歩行者への注意、環境の変化への対応。
屋外を移動するには様々な障害が待ち構えています。
これらをクリアしなければ、IADLの自立は不可能です。
④歩行の美しさ、スムーズさの獲得
人間というのは欲深い生き物なので、初めは歩けて喜んでいたのが徐々にそれでは満足できないようになっていきます。
そして最終的には「今までのように歩きたい、障害があるように見られたくない」という思いが出てきます。
私たちはそこにアプローチします。
歩ければいい、IADL上必要な歩行能力を獲得できればいいというのは理学療法士として求められる最低限の結果です。
さらにそこから1歩踏み込んで、美しく・スムーズに歩けるように練習してみてはいかがでしょうか。
今の歩き方を鏡やビデオなどで見せ、認識させてどうすればスムーズに歩けるのかを一緒に試行錯誤していくのも歩行訓練の効果として重要だと考えます。
誰だって「障害を持っている」と思われて生活するのは嫌です。
何とか正常歩行に近づける努力をすべきです。
対象のADLをイメージして歩行訓練をしよう
歩行訓練はただ歩かせればいいというわけではありませんが、ただ歩かせているだけの学生が多いのも事実。
歩行訓練は、しっかりと目標を持って実施していく必要があります。
目標は患者自身のHOPEだったり、自宅環境だったりで変わっていくので、設定を立てるのが大変ですが、学生はキチンと患者の欲求をくみ取り、歩行訓練として実施していくことを望みます。
- なぜその歩き方をさせるのか?
- なぜその距離を歩かせるのか?
- なぜその場所を歩かせるのか?
自問自答してみてください。
すんなりと答えがだせるようであれば、その歩行訓練は間違っていないのでドンドン練習していってください!
学生が良く使う歩行の評価
歩行訓練に入る前にしっかりと評価をしておくことが必要になります。
歩行の評価で有名な評価は
- 10m歩行
- 6分間歩行
バランス評価で有名な評価は
ぜひ評価項目も学習していってくださいね!