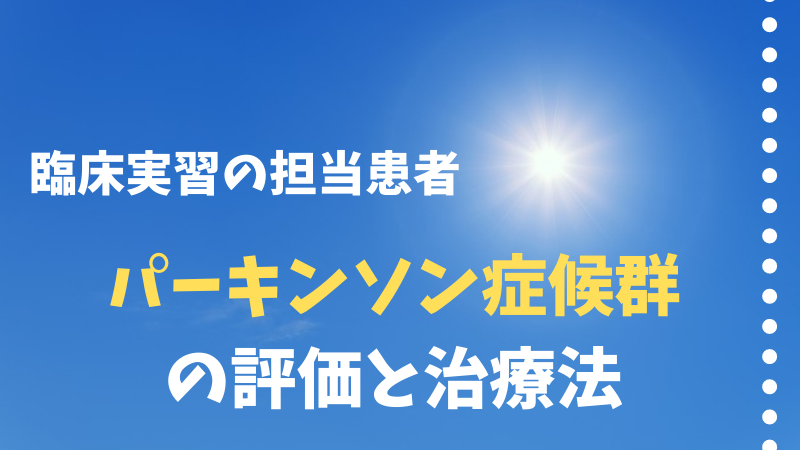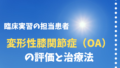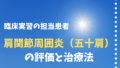各疾患には日本理学療法士協会が提唱する「理学療法ガイドライン」というものがあります。
過去の様々な研究や文献、論文から効果の有無や信頼性の高さを分類し、ガイドラインとして多くの理学療法士が作成しているもので、我々も臨床介入の参考にしています。
学生も、エビデンスのある介入をしていく必要があるので、ここでは分かりやすくエビデンスのあるもの(信頼性が高いとされているもの)をピックアップし、記載していきます。
教科書に載っていることも重要ですが、このガイドラインも重要ですのでぜひ臨床参加研修(臨床実習)の参考にしてください。
今回はパーキンソン病についてです。
中脳の黒質緻密層、青斑核などの脳幹部の変性・脱落を病変とする進行性変性疾患。
50~60 歳以降の高齢に発症することが多く、有病率は人口 10 万対 100~150 人程度とされる
【参考書】
パーキンソン病の疫学
- 静止時振戦、固縮、無動、姿勢反射障害の四大兆候を示す
- L-ドーパなどの抗パーキンソン病薬が使われる
- 抗パーキンソン病薬の副作用はwearing-off 現象、on-off 現象、ジスキネシア、幻視・幻聴など
パーキンソン病の実習で必須の理学療法評価法
パーキンソン病に対する評価項目をピックアップしていきます。
パーキンソン病の疾患特異的評価指標
- Hoehn & Yahr の重症度分類(Hoehn and Yahr staging scale: H&Y stage)
- パーキンソン病統一スケール(unified Parkinson’s disease rating scale: UPDRS)
Hoehn & Yahr の重症度分類
パーキンソン病の障害評価に用いられる。
対象者の症状を目安にⅠ~Ⅴの段階に表すのが特徴。
- Ⅰ:一側性で、片方に「固縮」「無動」「振戦」を示す。軽症。
- Ⅱ:両側性で姿勢反射障害が明確に出現。「固縮」「無動」「振戦」が両側に出て日常生活に不便をきたすが、介助は必要なし。
- Ⅲ:著名な歩行障害、姿勢反射が出なくなる。日常生活が困難であり、突進歩行も目立つようになる。日常生活の一部に介助が必要。
- Ⅳ:日常生活の低下が著しく、「固縮」「無動」「振戦」により立ち居振る舞い・排泄・着替えなどのADLに重篤な支障をきたす。
- Ⅴ:完全な廃用状態。開眼しているが振戦は常に出現し、車いすまたは寝たきりとなる。ADLは全介助。
パーキンソン病の身体機能に関する評価指標
- 歩行速度、歩幅、歩行率(gait speed,step length,stride,cadence)
- Berg balance scale(BBS)
- functional reach test(FRT)
- timed up & go test(TUG)
バーグ バランス スケール(Berg balance scale)
スコアから複数の転倒を予測できること、脳卒中の機能あるいは運動遂行能力と強い関係がみられることがBBSが推奨される理由です。
点数の低い項目=その動作で転倒しやすいということなので、その動作が日常生活に潜んでいないか観察しましょう。
ただし、実施する前に十分なバランス評価をしてから行いましょう。
危ないですから。

機能的リーチテスト(functional reach test: FRT)
簡単かつ再現性の高いテストとしてFRTもエビデンスレベルは高いです。
立位・座位で検査し、前方・左右と評価することでどちらに転倒しやすいか、またはバランスが良いか確認することができます。
これもぜひ評価しておきたい項目のひとつですね。
Timed “up & go” test(TUG)
慢性期脳卒中患者と健康な高齢者で TUG の再現性が確認されており、非常に有用な検査であることが示唆されています。
13.5秒以上で転倒リスクがあるとされていますが、指標の1つとしてください。
脳卒中患者に関しては、13.5秒以上かかっても丁寧に歩けていれば特に問題ありません。
突進歩行や小刻み歩行、ステッピングの消失などがなければ大丈夫だと思います。

パーキンソン病のquality of life(QOL)、精神機能に関する評価指標
- medical outcomes study 36-item short-form health survey(SF-36)
- 老年期うつ評価尺度:geriatric depression scale(GDS)
パーキンソン病に効果的な理学療法介入
パーキンソン病に対するリハビリをピックアップします。
もちろん、ここに載っていない治療法も効果がある場合が多いですので、参考までにどうぞ。
パーキンソン病の理学療法全般(exercise,physical therapy)
- 持久性運動、柔軟性運動、筋力増強運動、協調性・バランス運動を含む多様な運動実施
- 薬物療法と運動療法の組み合わせが良い
- バランス練習と合わせて筋力増強運動を実施すると良い
パーキンソン体操
https://www.taiyo-pharma.co.jp/wp-content/uploads/2020/07/mad_pdexe.pdf
パーキンソン病の筋力増強運動(muscle training,strength training)
- 筋力強化は効果を認める
- ボルグスケール7から13
- 四肢の柔軟体操、体幹筋力増強、エアロビクスなども有効
四肢柔軟体操
関節が固くなるのを防ぎ、動きを保つことを目的とする。
- 指を組んでゆっくり両手を上げ下げする
- 体を前後左右に曲げ伸ばしする
パーキンソン病のバランス運動(balance training,balance exercise)
- バランス訓練は有効である
- トレッドミル上での前後左右歩行
バランス訓練
転倒のリスクを減らすのを目的とする。
- 片膝立ちや四つ這いでの片手上げ
- 体幹のバランス訓練
- わざと体のバランスを崩し、それに対応できるようにする(バランス反応)
パーキンソン病の全身運動(aerobic training,aerobic exercise)
- トレッドミル、自転車エルゴメーター
- カルボーネン法による心拍数管理
歩行訓練
「突進歩行」や「すくみ足」などで転倒リスクが高くなるので、歩行安定性の向上を図る。
- 一定の間隔につけた目印をまたぎながら歩く
- 「1、2、1、2」と声をかけたり、メトロノームを使ってリズムよく歩く
- 数歩足踏みをしてから歩き出す
- スラローム歩行などの応用歩行
歩幅を大きくし、腕を振ることを意識させる。
パーキンソン病のトレッドミル歩行(treadmill training)
- トレッドミルの有効性は認められる
- 合わせてストレッチング、片足立ちなどの運動を取り入れる
パーキンソン病の在宅運動療法(home-based exercise)
- 膝屈伸運動、ステップ運動
- ストレッチング、関節可動域訓練、バランス訓練、歩行訓練、転倒予防教育
パーキンソン病の感覚刺激(sensory cueing)
- リズミカルな感覚刺激(聴覚、視覚、体性感覚)
- メトロノームの使用
- 1~2hzのリズム
パーキンソン病のリハビリまとめ
パーキンソン病に対しては筋力増強運動、バランス運動、全身運動、トレッドミル歩行などが有効です。
とくにいろいろな文献からトレッドミルの有効性が示唆されているので、ぜひチャレンジしてみたいですね。
治療プログラムの内容に関しては、患者の性格や病期の進行度合いによって異なるので正確な評価が求められます。
しかもその症状は色々とあるので、本当に全身を評価しなければならないので学生には少し大変かもしれませんね。
だからこそ、パーキンソン病の特徴を捉え、スムーズに評価・治療できるようにしていきましょう。
【参考】
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- パーキンソン病サポートネット
- 医療法人社団 吉田会 吉田病院
- 理学療法士の残業ゼロ生活
- 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 公益財団法人長寿科学振興財団